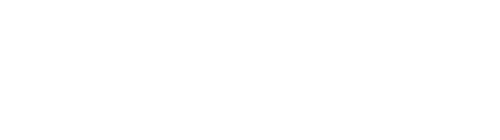【プログラム・ノート】
ヴォーカル・アンサンブル カペラ音楽監督 花井哲郎
L’homme, l’homme, l’homme armé,
L’homme armé
L’homme armé doibt on doubter,
doibt on doubter.
On a fait partout crier,
Que chascun se viengne armer
D’un haubregon de fer.
L’homme…
武装した人、その人、その人
武装した人、
武装したその人を恐れよ
恐れよ。
どこでも叫ばれている、
みな武装せよと、
鉄の鎖帷子(くさりかたびら)で。
武装した人….
ミサ《ロム・アルメ》
ルネサンスの時代に様々な作曲家によって数多く作られたミサ《ロム・アルメ》のなかでも、デュファイのミサ曲は最初期のものであり、おそらくはフランス宮廷楽長オケゲムによるミサ《ロム・アルメ》と共に最初の作品ではないかと考えられています。ミサの全楽章に定旋律として現れる勇ましい旋律「ロム・アルメ、武装した人」には、15世紀中頃のブルゴーニュ宮廷におけるフィリップ善良公(フィリップ・ル・ボン)を団長とする「金羊毛騎士団」の十字軍への呼びかけがその背景にあるようです。デュファイとオケゲムはおそらくは同時期にブルゴーニュ公に委嘱されてミサ《ロム・アルメ》を作曲したものと思われます。
この時代のミサ曲では、どのミサでも変わることのないミサ通常文を歌詞としていても、一つの定旋律を加え、その旋律を軸として楽曲を構築することで、5つあるミサ曲の楽章は一つのテーマを与えられます。聖母の賛歌「めでたし 海の星」”Ave maris stella”が使われるミサ《アヴェ・マリス・ステラ》は、聖母の祝日のためのミサ曲である、といった具合です。では戦闘がテーマのミサ《ロム・アルメ》は何のミサなのでしょうか。15世紀にはいささか時代錯誤的な発想でもあり、当然実行されることもなかった十字軍に関わるとはいえ、神聖なミサという儀式にはあまりふさわしくない内容とも思われます。教会で闘いというとその筆頭は、最大の悪である人類の罪と闘い、十字架での死と輝かしい復活によって、それに打ち勝ったキリストの闘いです。ミサの中でこの旋律が鳴り響く時、そこに勝利のキリストの姿を重ねることができるのかもしれません。
そういうわけでルネサンスのミサ曲では定旋律が何かということ、そしてそれをどのように作品の中で使っているか、ということが典礼の意味のうえからも、作曲技法的にも重要ではあるのですが、定旋律を聞く、ということが作品を味わう上で大事なこととは必ずしもいえません。それはあくまで骨組みなのであって、そこに肉付けされ、絡み合っていく様々な旋律、そして旋律の重なり合いによって生まれてくる和音が音楽を作っているわけです。
もちろん、定旋律が含まれていないセクションもたくさんあります。デュファイのミサ《ロム・アルメ》では各楽章の冒頭はすべてほとんど同じ音楽ですが、そこには定旋律は含まれていません。典礼の中では5つの楽章は祈祷や聖書朗読などを挟んでばらばらに演奏されますので、同じ冒頭主題があることで、時間をおいた後に歌われるミサ曲の各楽章が、同じテーマを持ったひとつの作品なのだということが思い起こされるのです。
キリエ
15世紀の作品の多くは二重唱で始まりますが、このミサ曲でもキリエ以外の4つの楽章の冒頭は、スペリウスとコントラテノールによる二重唱です。キリエだけは3つの声部による豊かな響きで開始されますが、グロリアと、そして特にクレドではかなり長い二重唱が冒頭主題の後に続いていきます。また、楽章の中間部分にも随所に、時にかなり長大な二重唱が挟まれていて、旋律を模倣し合ったり、音域が上下に交差したりして、二人の歌手による掛け合いが繰り広げられていきます。

【画像】ミサ《ロム・アルメ》よりキリエ
(MS Cappella Sistine 14, Biblioteca Apostolica Vaticana)
キリエでは3つの声部の冒頭主題の後にテノールがすぐに定旋律を厳かに加えて、ゆったりとしたペースで、途中二重唱部分での休止を挟んでキリエの3つのセクションとして定旋律全体を比較的分かりやすく歌っていきます。これは少し気をつけていれば聴き取ることができるのではないかと思います。
グロリアとクレド
しかし特に歌詞の多いグロリアとクレドの楽章では、意図的に定旋律がそれと認識されないようにカモフラージュされているようにすら思えます。テノールが担当する定旋律は、この2つの楽章では不規則に音価を伸ばしたり、休符を挟んだり、さらにはフレーズのおしまいに随意の旋律を付け加えて他の声部に紛れ込んでいくようなこともしています。ひとつの音が余りに長く引き延ばされてしまうと、前後の関連が分からなくなり、旋律として捉えられません。明らかに楽曲構成上のひとつの要素として定旋律を扱っているのです。
サンクトゥス
サンクトゥスの楽章は多くのルネサンスのミサ曲のように、5行の歌詞に対応して5つのセクションからなっていて、2番目 “Pleni sunt” と4番目 “Benedictus” は定旋律の含まれない二重唱(部分的に三重唱)です。3番目と5番目のセクションは共に同じ歌詞の “Osanna” ですが、16世紀のミサ曲によくあるように同じ音楽が反復されるのではなく、デュファイはそれぞれに違う楽曲を作っています。そして2回目の “Osanna” ではひとつのセクションの中で、定旋律をリズムも原曲通りに組み込んで、その全体を聴き取ることができるようになっています。
特に勇ましく勝利のキリストを彷彿させる旋律であることもあって、定旋律が凱旋の歌のように鳴り響くわけです。ルネサンスの時代、長いサンクトゥスの楽章が歌われている間に、祭壇ではパンとぶどう酒を聖別する儀式が進み、聖変化によってそこにキリスト御自身が臨在することになります。まさにそのタイミングで「ロム・アルメ」全曲が高らかと聞こえてくるので、象徴的な意味を感じ取ることもできるかもしれません。
アニュス・デイ
「ロム・アルメ」の旋律が特に良く聴き取れる、あるいはむしろそれとしてはっきり提示されているようなところが2箇所あります。キリエの最後と、アニュス・デイの最後で、この部分は音楽的には全く同一です。そしてそこでは音価が半減され、つまり特別に早いテンポで歌われます。そのことで旋律として際立って聞こえるのです。キリエの最後の部分では、定旋律の最後の1行だけをこの速いテンポで歌います。アニュス・デイでは最初から定旋律全体を速いテンポで歌いますので、キリエと同一の部分はその最後の部分、ということになります。
このアニュス・デイの第3セクションにはもう一つ仕掛けがあります。テノールの声部に演奏上の指示書きが添えられています。
Cancer eat plenus sed redat medius
全体を蟹歩きで、しかし戻りは半分で
左右に行ったり来たりする蟹のように、記譜されている定旋律を1回目は後ろから前に、つまり楽譜の最後から左方向に逆に読んでいき、最初にきたら今度はそこから普通に右方向に順番に読む、しかし音価は書かれている長さの半分で、つまり倍速で歌うということです。そういうわけで2回目はとても分かりやすいのですが、1回目は定旋律として意味をなさず、聞いていても何だか分からない、闇の旋律です。
アニュス・デイ「神の小羊」とは人類の罪をあがなうために十字架上で生贄として殺された神の子キリストのことです。逆さまの旋律はその死、倍速の2回目は死の克服、勝利の歌、と聞くこともできるかもしれません。
デュファイの名作ミサ曲というと有名なミサ《スラファセパル(私の顔が青いのは)》があります。優雅なシャンソンを定旋律としていて、その音価は2倍、3倍と拡大されますが、全体の構成は理路整然としています。その基盤の上に実にバランスのとれた、聞きやすい麗しい音楽が展開していきます。それに比べると本日のミサ《ロム・アルメ》定旋律の扱いだけとってもかなり癖があり、デュファイが工夫を凝らした跡が見て取れます。
工夫に満ちた楽曲構成
さらにこの曲を独特の響きにしている要素があります。「ロム・アルメ」の旋律は作曲家によっていろいろな旋法でミサ曲に組み込まれます。原曲はソソドドシラソ、いわば長調的な旋法ですが、このミサ曲ではレレソソファミレという短調的な旋法になっています。それをテノールの音域に合わせるためにフラットを1つ付けて4度上に「移調」してあります。いわばト短調的な旋律となっています。それに合わせてコントラテノールとバッススの声部にもフラットが1つ加えられているのですが、スペリウスにはありません。冒頭主題をお聴きになるとすぐに分かりますが、そのために始まりはト長調的な明るい響きがします。しかしすぐに他の声部が短調的な和音を作っていきますので、長調と短調が交互に出てくるような不安定なことになってしまいます。
極めつけは二重唱の模倣で、スペリウスはフラットなしに歌うのに対して、同じ旋律にコントラテノールはフラットを付けるので、居心地の悪い模倣となってしまいます。幸いルネサンス音楽には「ムジカ・フィクタ」という、演奏者判断でシャープやフラットを付けていく習慣がありますので、あまりに不自然なところ、ひどい不協和音的になってしまうような箇所にはスペリウスにもフラットを付けることができます。しかしながら、この「対斜」の状況を生み出す不安定な半音関係は、独特な魅力を与えるためにおそらくはデュファイが意図したものであって、可能な限り記譜通りに歌っていくのがいいのだと思われます。
この長調短調の交錯に加えて、もう一つの要素にリズムのぶつかり合いがあります。いわば2拍子で進んでいるところに突如1つの声部だけ3拍子のリズムを加えてきます。それもいろいろな音価のレベルでそれが行われるので、時としてかなり複雑なリズム関係が生じます。それが端的に表れているのが、クレドの楽章の “Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt” 「造られることなく生まれ、父と一体。すべては主によって造られました」の箇所です。4つの声部がそれぞれ全く関連のないリズム体系なので、かなり混沌としていて演奏も困難ですが、突如として現れるカオスに聴いている人も困惑するのではないかと思います。「すべては主によって造られ」のすべてが表現されているということでしょうか。
デュファイ世代に始まったミサ《ロム・アルメ》の伝統はその後16世紀いっぱい続いていきますが、デュファイのこのような技巧の粋を尽くした、工夫に満ちた楽曲構成の仕方そのものが後の作曲家たちにも引き継がれ、代々のミサ《ロム・アルメ》はどの曲も他には見られないような力作ばかりです。
モテット「闘う教会」
キリストの次に、闘う者としてふさわしいのは大天使聖ミカエルです。ヨハネの黙示録12章には、天の戦いでミカエルを始めとする天使たちが竜、サタンと闘ったことが記されていて、聖画でも鎧を身につけて剣をかざし、ドラゴンを踏みにじっている姿で描かれる、キリストの旗手です。ミサ《ロム・アルメ》が歌われる典礼として、本日は9月29日大天使聖ミカエルの祝日のミサとして、その日に歌われるグレゴリオ聖歌、祈祷、朗読などと共にプログラムを組みました。この日のみに歌われるミサ固有唱の旋律は、デュファイが住んでいたカンブレという北フランスの街に伝わる聖歌集から取りました。16世紀のものですが、そこにはおそらくはデュファイ自身が作曲したと考えられる聖歌も含まれています。ザンクト・ガレンを始めとする中世の旋律と比べるとだいぶ単純化されて、コンパクトな形になっています。
プログラム最後はいわゆるアイソリズムのモテット「闘う教会」 “Ecclesiae militantis” です。デュファイのアイソリズム・モテットとして有名な「ばらの花が新たに」”Nuper rosarum flores” と同様、教皇エウジェニウスをたたえる作品です。教皇選出を祝って作られたことが歌詞から分かります。14世紀からの伝統的なモテットの形式であるアイソリズムでは、グレゴリオ聖歌などの旋律の一部を音素材として切り取ってテノール声部に配置し、そこに一定のリズムパターンを付加していき、それを何回か反復します。音素材とリズムパターンがずれて不規則になっていくのが中世の特徴ですが、デュファイはそれを完全に一致させて、ただし反復時にはメンスーラを変えて、つまり同じ旋律を違う拍子、違う音価で反復するように仕組みます。そういう意味ではアイソリズム・モテットというよりはメンスーラ・モテットと言うべきという主張もあります。

【画像】「闘う教会」“Ecclesiae militantis” のテノール声部
このモテットでは2つのテノール声部がそれぞれ9音、3音からなる旋律素材を6つの異なるメンスーラで繰り返していきます。第2テノールの「ガブリエル」という歌詞は、カントゥス1の歌詞が述べているように教皇の洗礼名です。この長い音価のテノールの上に3つの声部がそれぞれに異なる歌詞で教皇エウジェニウスのことを語っていきます。そのうちコントラテノールの声部は、同じ楽曲を同じ歌詞で3回繰り返します。その2回目はメンスーラを変えて、2:3の割合で他の声部に食い込んでいきます。こういった複雑な作りはミサ《ロム・アルメ》と同じ精神だと言えましょう。5つの歌詞が同時に歌われて到底聴き取れませんので、文字で読んで理解することが前提となっているわけです。
野心的な作品ばかりですが、その複雑さを超えたところから降り注いでくる、デュファイの天才的な響きの世界に身をまかせ、大天使聖ミカエルの導きの元、天の世界へ心を挙げて頂ければ幸いです。